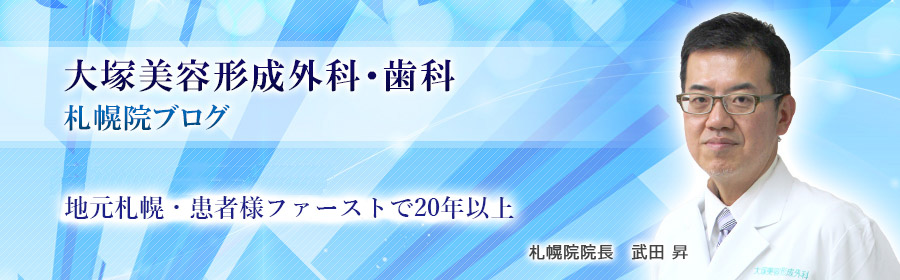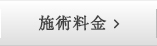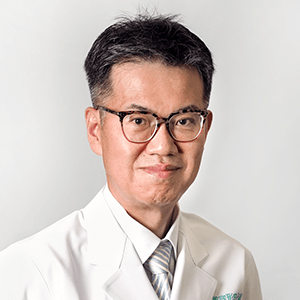先週まで、最近話題に上るiPS細胞というものが、人工の細胞であると言うこと。
何を原材料として作成しているのかということをお話してみました。
T細胞と言う血液の細胞からiPS細胞を作成する方法は、0.5ccの血液があれば作成可能な方法で、新生児でも作成可能です。採血してから24時間後でも作成可能なことから、死亡した後に採血したとしても、地理的に恵まれない人も作成できる。また昨日述べたように、遺伝子を傷つけずに作れるという利点が上げられます。
次はそのiPS細胞を特定の組織に誘導していく段階です。
それには、今までES細胞で培ってきたテクニックを用いて、色々な細胞に育て上げていきます。
この仕事は、現在厚労省が国家プロジェクトと位置付け、莫大な予算が投じられているため、日本中の研究者が色々な細胞を作るのに挑戦しており、あまりに多岐に及ぶため、今日は、心筋細胞に的を絞ってお話してみたいと思います。
iPS細胞を元に心筋細胞が出来たとします。フィブリン糊という培地の上で培養して増やせば、シート状の心筋細胞でできた組織が出来上がり、心筋の一番の特徴、生涯動き続けるという特性のまま、ねずみの背中に貼り付けたシートでも動き続けるのが観察することが可能な細胞の塊が出来ます。
それを実際の臨床ではどう用いられているのか、あるいはどう使おうとしているのか。
一番人類に福音をもたらすのは、恐らく難病の解明についてだと考えられます。
具体的に行われている事例では、QT延長症候群と言って若年者の突然死の原因の一つになっている病気の解明です。
この病気は、心臓の伝達系の異常の一つですが、心臓の滑らかに心筋を興奮させ収縮させ拍動を起こすという連鎖がうまくいかず、突然の心室細動、心拍出の低下、失神、死と続く恐ろしい病気です。
iPS細胞から、QT延長症候群の患者様と同じ心筋を作り出し、その原因、薬物の効果などを調べていき、有効な治療法を見つけようとしている仕事が、慶応大学の循環器内科などで行われています。
これは、非常に裾野が広い応用が考えられ、薬の人体に対する副作用、毒性などの調査にも使える、画期的技術進歩と言えます。
もちろん実際の虚血性心疾患などで心筋を奪われた患者様への臨床応用も研究対象です。
胸部外科領域で心筋シートを作成して、実際に心筋梗塞を起こした部位に貼り付ける治療が新聞報道されていましたが、内視鏡で心臓に心筋細胞を針で打ち込む治療も始められようとしてます。
世界のオリンパスが心嚢カメラという心臓を直接見れる内視鏡を開発し、心臓の血管をよけながら、心筋細胞を心臓の弱った部位に注射することで移植していくわけです。
美容領域での臨床応用も遠い日の出来事ではありません。
先日も、大手化粧品メーカーが、iPS細胞を用いて作成した皮膚モデルで皮膚の老化の防止に関する研究を行うと報じられていました。
次回、さらに掘り下げて、再生医療についてお話ししていきます。
冬期間は雪に閉ざされる札幌。秋になるとgardeningの道具も大幅に値引きされます。
それを狙って、少し庭を改修しました。
雪が降る前に、もう一度BBQをしようかと考えています。