銀座本院0800-222-1611
札幌院0800-888-1611
金沢院0800-888-1614
京都院0800-888-1615
直通フリーダイヤル


まぶたの脂肪が厚い場合には、マイクロ切開(自然癒着法)を併せて行うことで、よりまぶたをすっきりさせることが可能です。ただし、眼窩脂肪の切除によってかえって老けた印象になる場合もありますので、経験豊富な医師による見極めが大切です。
今回のモニターさんは60代です。目が重たい感じがすることと、見えにくい感じがするようになったため来院されました。施術前のまぶたの状態は「皮膚がまつ毛に乗っかっている」「まぶたが窪んでいる」「眉毛が上がっている」「額にシワがある」といった症状が見られました。
当院のフォーエバーブリリアント埋没法プレミアムは「固定が長い」ので、しっかりとまぶたのタルミが取れます。施術後の画像でもまぶたのタルミがしっかりと取れたことがわかります。他院では眼瞼下垂の手術を勧められたようですが、切開しなくても二重幅を調節することにより自然でタルミのない若々しい目元となります。
| 手術名 | フォーエバーブリリアント埋没法(FB法) |
|---|---|
| 費用 |
3連結線留め(5年保証)
両目…¥165,0004連結線留め(10年保証)
両目…¥275,000 |
| リスク・副作用 | 二重の消失、縫合糸膿瘍等の感染症、埋没した糸の透見、目の異物感、術後の腫脹、内出血、目の違和感等 |
| 所要時間 | 約20分~30分 |
| ダウンタイム | 3日~4日 |
| 腫れ・傷跡 | 腫れはそれほどありません |
| 施術の痛み | なし |
| 通院 | なし |
| 麻酔 | 点眼麻酔・局所麻酔 |
| 持続性 | 5年間 |
| 洗顔 | 当日から可能 |
| シャワー・入浴 | シャワー:当日可 入浴:1週間後から可 |
| メイク | 2日後から |
| 施術名 | 場所 | 定価(税込) | 保証 |
|---|---|---|---|
| 3連結線留め | 両目 | ¥165,000 | 5年 |
| 4連結線留め | 両目 | ¥275,000 | 10年 |
石井医師限定「腫れにくい」埋没法
| 施術名 | 回数 | 定価(税込) | 保証 |
|---|---|---|---|
| <腫れにくい> 3連結線留め |
両目 | ¥297,000 | 10年 |
| <腫れにくい> 4連結線留め |
両目 | ¥363,000 | 10年 |
| ※腫れ止めセットの費用も施術料金に含まれます。 | |||
※自由診療のため保険適用外となります。
| オプション | 料金(税込) |
|---|---|
| 34G極細麻酔針 麻酔時の痛みを軽減する極細の針 |
¥4,400 |
| リラックス麻酔 麻酔時の痛みを軽減する麻酔 |
¥11,000 |
| 「シンエック」12錠 腫れを少なくする回復促進サプリ |
¥7,700 |
| 【腫れ止めセット】 34Gの麻酔針2本+シンエック12錠 |
¥14,300 |
| 冷却マスク | ¥1,100 |

小さな手術で大きな効果を
創立以来の当院の基本理念です。
患者様の心身のご負担を少しでも取り除くことができる手術の提案をし、また、患者様のご希望をきちんと理解することで、効果を導き出しています。

経験に基づく技術と豊富な症例数
1976年の大塚美容形成外科開院以来、国内外の多くの学会発表の経験があり、その研究成果や実績を活かした施術を行っています。

医師による丁寧なカウンセリング
当院では医師がカウンセリングを行っています。手術方法だけではなく、メリット・デメリットについても医師が丁寧に説明します。また手術後は、24時間受付OKのメール相談や緊急連絡先にご相談いただけます。
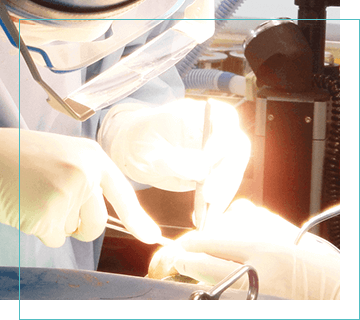
確立された技術力
経験を積んだ形成外科専門医・美容外科医が在籍し、日々技術力の向上に努めています。
また更なるスキルアップのため医師同士の意見交換会も実施しています。
医師が直接カウンセリングを行い
適切な治療のみご案内いたします。
無理に施術をすすめたり
当日中に契約を迫ることは一切ありません。
大塚美容形成外科は全国4院。
お近くのクリニックで、
カウンセリング・施術を
お受け下さい。
大塚美容形成外科では、2018年6月に改正・施行された「医療広告ガイドライン」遵守し、総院長石井秀典医師監修のもと、患者様に正確な情報をお伝えすることを目的とし、当サイトの運用を行っております。
| 監修医情報 | |
|---|---|
|
大塚美容形成外科 総院長 石井秀典 (いしいひでのり) |
|
| 経歴 |
2000年 帝京大学医学部 卒業/2000年 帝京大学医学部形成外科 入局 2005年 杏林大学病院 形成外科 入局 2006年 大塚美容形成外科 入局 2006年 医学博士号 学位取得 2022年 大塚美容形成外科 総院長就任 帝京大学医学部 形成外科 非常勤講師 |
| 資格・取得専門医 | 医学博士 日本形成外科学会専門医 日本美容外科学会専門医(JSAPS認定) アラガン社ファカルティ(ボトックス・ヒアルロン酸注入指導医) |
| 所属学会・団体 | 日本美容外科学会(JSAPS)正会員 日本形成外科学会会員 国際形成外科学会会員 日本頭蓋顎顔面外科学会 日本創傷外科学会 |